 |
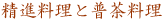
|
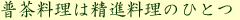
精進とは仏道を完成する精神修養の根幹をなすもので、 現代の仏教における「精進料理」の伝統には
大きな二つの流れがあります。 いずれも禅僧によって中国から伝えられたものですが、 ひとつが「永平寺流」精進料理、 そしてもうひとつが「普茶料理」となるわけです。
|
「永平寺流」精進料理
|
曹洞宗の開祖・道元が鎌倉時代の初期に留学先の中国から持ち帰ったもので、 料理することも、またそれを頂戴することも、同じように修業のひとつの形である
とするものです。この「永平寺流」精進料理の食事礼法は茶懐石の原型となります。
|
 |
「普茶料理」
|
黄檗宗に伝わる「中国風」精進料理で、 江戸時代初期、京都の宇治に萬福寺を開いた明の帰化僧・隠元禅師が伝えたものです。
永平寺流の精進料理が食即ち修行とみるのに対し、飲食平等の趣旨を持ち、食そのものを楽しみます。
普茶料理の基本形式は他の精進料理とは違い、銘々膳ではなく、席に上下の隔てもなく、 1卓は4人というのが基準です。皿、鉢などに取箸はなく、各人の箸で自由に取って食べます。
|
梵での普茶料理例  |
 |
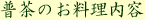
お料理の特徴
豆腐、ごま油を多用し、食用の野草から花まで、あらゆる野菜を用い、 材料の持ち味を十分に生かして調理する点にあります。
普茶料理の例
・箏羹(しゅんかん):竹の子を中心とした季節の野菜乾物等の煮付
・油茲(ゆじ):野菜の味付け天麩羅
・麻腐(まふ):胡麻豆腐
・雲片(うんぺん):野菜を単冊に切り、油煎りして葛煮にしたもの
・擬製料理(精進材料で魚や肉の擬製品を作る料理)
- 豚肉=わらび粉を練り、薄く伸ばして形作り、油でいため揚げる。
- 鶏肉=くわいをすりおろし、味をつけて丸め、油で揚げる。
- 卵=いり豆腐をくちなしで黄色に染める。
- うなぎの蒲焼=豆腐をすったものに、おろした山芋を混ぜて形作り、のりを片面にはって油で揚げ、さらに照り焼きにする。
- 黄檗まんじゅう=デザート用のごまやくるみあんをいれた焼き菓子。
|
 |
[参考文献]
「精進料理大事典」仏教料理研究会編
|
   |